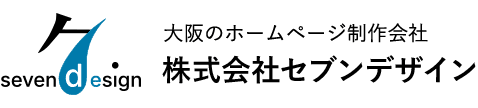- 公開日: 最終更新日:
ChatGPTが書いたAI文章はバレる?人間らしい文章に直す方法

ChatGPTを使ってホームページ制作を行うのが一般的になりつつありますが、ChatGPTが書いたAI文章は一見自然でも、どこか機械的に映ることがあります。読んでいて違和感を覚えたり、人の気配が感じられないと、せっかくのコンテンツも最後まで読まれずに離脱されてしまいます。
このページでは、ChatGPTが書いた文章がなぜバレてしまうのか、その理由やデメリット、そして人間らしい文章に仕上げるための方法について解説します。
目次
ChatGPTが書いたAI文章がバレる理由
一見自然に読めるChatGPTのAI文章でも、読み手やアルゴリズムは思いのほか敏感にAIっぽさを感じ取ります。それは、AIが生み出す文章には人間にはあまり見られない共通の特徴があるためです。ここでは、ChatGPTが書いたAI文章がバレる理由を解説します。
内容が一般的すぎる
ChatGPTは大量の文章データを学習して、もっともらしい平均的な答えを生成するため、内容がどうしても無難で一般的になりがちです。
一見すると整っていて読みやすいように見えても、深掘りされた考察や独自の視点、現場で得た具体的な知見が含まれないため、情報に厚みがなく表面的な印象を与えてしまいます。
こうした平均的な答えばかりが並ぶと、読者には情報が浅く感じられ、独自性の欠如からAIが書いたと見抜かれる大きな要因になります。
感情や主観が薄い
ChatGPTはあくまで確率的に言葉を並べるため、感情や主観がほとんど含まれません。喜び・驚き・迷い・葛藤といった人らしい揺れがないことで、文章全体が無機質な印象になります。
たとえば、「このツールはとても便利です」と述べるだけでは、読み手には感情が伝わりません。人が書くなら「このツールを導入してから作業時間が半分になり、本当に驚きました」と感情と背景を添えるのが自然です。
感情の欠如は、読者の共感や没入を妨げるだけでなく、「人の気配がしない=AIっぽい」と判断される決定的なポイントになります。
表現のバリエーションが乏しい
ChatGPTは豊富な語彙を持つように見えますが、実際には限られた表現を繰り返す傾向が強く、パターンの単調さからAIと気づかれることがあります。
たとえば、段落の冒頭が「まず」「次に」「そのため」といった定型の接続詞で始まり、文末も「〜です」「〜します」が連続するなど、言葉のリズムや抑揚に変化がないことが多いです。
人間が書いた文章には、自然な言い換えや表現のゆらぎが含まれます。一方でChatGPTが書いた文章は構造的に整いすぎているため、「上手だけどどこか単調=AIっぽい」と感じさせてしまうのです。
構成が整いすぎている
ChatGPTの文章は、論理構造がきれいにまとまりすぎていることが多く、人間らしい揺らぎや寄り道がないのが特徴です。
一文一文のつながりも常に滑らかで、論点が破綻することがほとんどありません。一見メリットに見えますが、実際の人間の文章には、強調したい点であえて話を脱線させたり、読み手を引き込むために感情的・感覚的な余白を入れたりする自然な乱れがあります。
AIの文章はそれが欠けているため、完璧すぎて不自然と感じられやすいのです。読者は無意識にこの違いを察知し、「これは人間の言葉ではない」と直感的に見抜くことがあります。
多くのAIチェッカーがある
近年では、AIが書いた文章かどうかを判定するAIチェッカーも数多く登場しています。文体のパターンや確率分布を解析し、AI特有の癖をスコア化して判定する仕組みです。
これらのツールは完璧ではなく、あくまで推定に過ぎませんが、一定の傾向を高い精度で検出できるレベルに達しており、実際にWeb業界でも活用が広がっています。
つまり、AI文章では、見た目は自然でも判定には通らないという状況が起きやすいのです。
ChatGPTが書いたAI文章のデメリット
ChatGPTを活用すれば効率的に文章を作成できますが、その一方で注意しておきたいデメリットも存在します。ここでは、ChatGPTが書いたAI文章のデメリットを紹介します。
SEO効果が出ないことがある
Googleは、「AIが文章を書いていても、ユーザーにとって有益であれば評価する」と明言しています。つまり、AI生成そのものはSEO上のマイナス要素ではありません。
しかし、ChatGPTが出力した文章をそのまま掲載すると、ユーザー目線になっていないことが多く、検索意図に合わずに離脱されやすい傾向があります。結果として、評価が上がらずSEO効果が発揮されないケースが少なくありません。
AIを活用する場合でも、読者のニーズに合わせて内容を整えることが欠かせません。
AIが書いているだけで読む気が失せるユーザーがいる
AIが書いたと感じた瞬間に読む気がなくなるというユーザーは少なくありません。
理由はさまざまですが、感情が感じられないや本当にその人の言葉なのか分からない、どこか薄っぺらく感じるといった印象を持たれてしまう、AIで作ったものは信用できないと感じられてしまうことが大きいです。
そういった読者にとっては、人が書いているかどうかが判断基準になっているケースもあるため、AIであることがわかった瞬間に興味を失うことも珍しくありません。
つまり、文章がAIによるものだと伝わってしまうだけで、読む気そのものが失われてしまうリスクがあるということです。見た目が整っているだけでは読まれず、読まれなければどんなに情報を詰め込んでも意味がなくなってしまいます。
運営者に知識が蓄積されない
文章を自ら書くという作業には、自社の知識や考えを整理する効果があります。
リサーチを通じて新たな視点を得たり、伝えたいことを言葉にする過程で、自分たちの強みや方向性を再確認できる場面も少なくありません。しかし、ChatGPTに全てを任せてしまうと、その過程が省略されてしまい、学びや気づきが生まれにくくなります。
さらに、ノウハウを内製化していくためには、何をどう伝えるかを社内で共有し、ブラッシュアップしていく仕組みが必要です。AIに依存したままだと、担当者の経験値も積み上がらず、外注的な運用になってしまいます。
短期的には便利でも、長期的に見ると社内にコンテンツ力が根付きにくくなるというデメリットがあります。
ChatGPTのAI文章を人間らしい文章に直す方法
ChatGPTが生成した文章は、一見きれいでも、読み手からは機械的で無機質に感じられることがあります。そのため、ChatGPTが書いた後、必ず読み直しを行い調整する必要があります。ここでは、ChatGPTのAI文章を人間らしい文章に直す方法を紹介します。
文末や接続詞の単調さを整える
ChatGPTの文章は、「〜です。〜します。」といった同じ文末や接続詞が続く傾向が強く、読み手に単調な印象を与えます。
まずは文章全体を読み返し、語尾や接続詞のバリエーションを増やすように整えましょう。たとえば、「そして」「そのため」「しかし」が連続していれば、「さらに」「一方で」「とはいえ」などへ置き換えてリズムを変えると、人が書いたような自然な流れになります。
この工程だけでも、文章に温度と抑揚が生まれ、機械的な印象をやわらげる効果があります。
感情や主観を加える
AIは客観的な事実を並べるのは得意ですが、感情や主観がほとんど含まれないため無機質に見えます。
そこで、自分自身の経験や感じたことを1〜2文加えることで、文章に人の気配を与えることができます。たとえば、「便利です」だけで終わらせず、「作業時間が半分になって、本当に助かりました」と書き添えると、読者は筆者の感情に共感しやすくなります。
感情表現を加えることで、読者の没入感や信頼感を高める効果があります。
具体例や体験談を差し込む
抽象的な説明では、人が書いた文章には見えにくいため、具体的な事例や実体験を盛り込むことが効果的です。
たとえば、「問い合わせ数が増えました」と書くより、「導入後1ヶ月で問い合わせ数が2倍になりました」と数字や背景を添えると、内容にリアリティと説得力が加わります。
また、日常の小さなエピソードでも構いません。体験談を交えるだけで文章にオリジナリティが生まれ、AIっぽさを大きく薄めることができます。
事実関係や根拠を確認する
ChatGPTは自信たっぷりに誤ったハルシネーションを出力することがあります。
そのため、生成された内容は必ず一次情報や信頼できる資料で裏付けを取ることが重要です。誤情報をそのまま掲載してしまうと、読者の信頼を失うだけでなくSEO評価も下がるおそれがあります。
読みやすさ以前に正確さを担保することが、人間らしい文章の前提条件です。
自分の言葉に置き換える
AIが書いた文章は、論理的でもどこか他人行儀で、筆者固有の視点が感じられにくいのが特徴です。
一度全文を読み直し、「自分だったらどう表現するか」を意識して言い回しを自分の言葉に置き換えると、一気に人間らしさが増します。
語順を少し変える、言葉を口語に寄せるだけでも効果的です。文章に筆者の個性や視点が宿ることで、読者は本当に人が書いていると感じやすくなります。
AIチェッカーなどで違和感を最終確認する
最後に、AIチェッカーなどを使って文章全体を客観的にチェックするのも効果的です。
スコアは絶対ではありませんが、AIらしさが残っていないかを見直すきっかけになります。同時に、音読してみるのも効果的です。声に出して違和感がなければ、人間らしい自然な文章に近づいていると判断できます。
最終確認の工程を入れることで、仕上がりの品質を安定させられるようになります。
まとめ:ChatGPTのAI文章はバレることを理解して活用しよう
ChatGPTで生成されたAI文章は、一見すると自然に見えても、読者によっては違和感を覚えることがあります。語尾の繰り返しや機械的な言い回しが原因となり、人が書いた文章との違いに気づかれることがあります。
Googleは、AIが書いたこと自体を問題視しているわけではなく、あくまでもコンテンツの品質を重視しています。読者にとって役立つ情報であれば、AIによる文章でも正当に評価される可能性があります。
とはいえ、読み手がAIっぽさを感じてしまえば、途中で読むのをやめたり、信頼性を疑ったりするリスクがあります。そうした離脱を防ぐためにも、文章の内容や表現に人間らしさを加える工夫が必要です。
ChatGPTを使い、誰がどんな目的で、誰に向けて書くのかを意識し、経験や感情を加えて仕上げることで、より伝わるコンテンツになります。AIを使いこなしつつ、人が読む文章として自然に整えていく姿勢が必要です