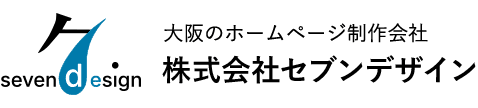- 公開日: 最終更新日:
Webデザインの希望をデザイナーに正しく伝える方法
Webデザインを依頼した際に、仕上がりがイメージと違っていたという経験は少なくありません。その原因の多くは、希望や意図の伝え方にあります。
この記事では、Webデザイナーに希望を正しく伝えるための具体的な方法や、うまく伝わらなかったときの対処法を紹介します。スムーズなやり取りで理想のデザインに近づけたい方はぜひご覧ください。
目次
なぜWebデザインの希望を伝えることが重要なのか
Webデザインを依頼するときに大切なのは、何を作りたいのかをデザイナーにきちんと伝えることです。希望するイメージや目的が明確であれば、デザイナーも方向性を把握しやすく、レイアウトやビジュアルの設計がスムーズに進みます。
あらかじめ伝える内容を整理しておけば、認識のズレが起きづらく、イメージ通りの仕上がりが期待できます。反対に、希望が曖昧だったり、伝え方に一貫性がなかったりすると、完成品が思っていたものと違うという結果になりかねません。その結果、修正が繰り返されて納期が延びたり、費用が膨らんだりすることがあります。
特にWebデザインは、見た目だけでなく、操作のしやすさや情報の見せ方なども含めた総合的な設計です。たとえば、ブランドをどう見せたいのか、どんなユーザーがどう使ってもらうのかといった視点が欠かせません。
希望する機能やイメージ、参考にしたいサイトなどを事前に共有しておけば、デザイナーも判断しやすくなります。完成度の高いサイトを作るには、制作前の情報共有が何よりも重要です。
Webデザイナーに希望を正しく伝える方法
理想に近いWebデザインに仕上げるためには、希望や要望を正確に伝えることが欠かせません。ここでは、具体的にどのような内容をデザイナーに共有すればよいかを解説します。
Webデザインの目的やターゲットを共有する
Webサイトを通じて、何を達成したいのかを明確にすることが、まず大前提です。
企業の信頼感を高めたいのか、集客を狙いたいのか、それとも採用情報を届けたいのか。目的によってデザインの方向性は大きく変わります。
また、ターゲットとなるユーザー層や行動傾向も、デザインに大きく影響します。たとえば、若年層向けであればトレンドを取り入れた動きのあるデザイン、中高年層が対象であれば視認性や操作性を重視した落ち着いた構成が求められることもあります。
サイトの目的やターゲットをあらかじめ共有しておくことで、デザイナーはその意図に沿った設計をしやすくなり、ブレのないデザインに仕上がります。
希望のカラーを伝える
サイト全体の印象を左右するのが色です。
コーポレートカラーやブランドカラーがある場合は、それを必ず共有しましょう。また、特に指定がなくても、ターゲットに好まれやすい色合いや、避けたい色などを伝えておくと、色味のミスマッチを防げます。
カラー指定は、信頼感・安心感・先進性・楽しさなど、伝えたい印象とも深く関係しています。色に関する要望を具体的に伝えることで、方向性のズレを減らすことができます。
ブランドイメージを共有するための素材を渡す
ロゴやパンフレット、名刺など、すでに存在しているブランド要素をデザイナーに提供することで、Webデザインとの一貫性が生まれます。
これにより、ブランドの世界観がぶれずに伝わり、ユーザーへの印象も安定します。特にトーンやスタイルに関わる情報は、文章で説明するよりも実際のビジュアル素材を見た方が圧倒的に伝わりやすく手戻りも減ります。
必要な機能を伝える
Webデザインには、見た目だけでなくどのような動きを持たせたいかやどんな機能が必要かも含まれます。
たとえば、トップページのスライダー、メニューのアニメーション、問い合わせフォームの仕様などです。これらの情報が事前にあることで、デザイナーは構成や動線、レイアウト設計に必要な考慮を行えます。
どのページにどの機能が必要か、どの機能を優先するかなど、詳細を具体的に伝えることが、納得のいくデザインへの近道となります。
参考サイトを提示する
イメージに近いWebサイトを提示するのは非常に有効です。
好きな配色、レイアウト、フォント、メニューの動きなど、具体的に、どこが良いと感じたかをメモして伝えると、デザイナーが感覚を掴みやすくなります。逆に、こういう雰囲気は避けたいといったNG例もあると、仕上がりのズレを未然に防げます。
複数の参考サイトを共有する場合は、比較対象となるように、評価ポイントも添えて伝えると効果的です。
デザインデータの納品形式を伝える
制作後の管理や編集をスムーズに行うために、納品形式を事前に確認しておきましょう。Photoshop、Illustrator、Figmaなど、使用ソフトによって納品データの扱いが異なります。
また、自社で更新を行う場合は、編集可能な状態でデータをもらえるよう依頼しておくことが重要です。納品段階でのトラブルを防ぐためにも、形式・編集・ファイル構成の希望などを事前に明確に伝えておくと安心です。
希望納期を伝える
納期の希望は、なるべく早い段階で具体的に伝えましょう。
いつまでに完成してほしいかだけでなく、いつデザイン案を確認したいか、修正対応はいつまでかなど、中間ステップも含めて共有しておくと、スケジュールのズレを防げます。
短納期で対応をお願いする場合は、優先度の高いページから順に制作していくなどの方法も検討するとよいでしょう。制作側と進め方の認識を揃えることで、より効率よく進行できます。
うまくWebデザインの希望が伝わらないときの対処法
希望通りに伝えたつもりでも、完成したデザインを見てなんか違うと感じることは少なくありません。そんなときは、伝え方や関係者との連携を見直すことで、ズレを修正しやすくなります。ここでは、希望がうまく伝わらなかったときに試したい対処法を紹介します。
イメージが伝わらないなら依頼書を使う
伝えたいことが口頭やメールではうまく伝わらないと感じたときは、依頼書の活用が有効です。
依頼書には、サイトの目的やターゲット、デザインイメージ、必要な要素、参考サイトなどを整理して書き出します。書面にすることで情報が可視化され、認識のズレが生まれにくくなります。
また、デザイナー側も後から内容を見返すことができるため、細かいニュアンスの共有や制作精度の向上につながります。特に社内で複数人が関わるプロジェクトでは、依頼書をベースに話を進めることで、情報の一貫性を保ちやすくなります。
打ち合わせにWebデザイナーを同席させる
担当者とデザイナーの間にディレクターや営業が入っている場合、情報が間接的に伝わってしまうことがあります。このようなケースでは、打ち合わせにデザイナー本人を同席させることで、希望のニュアンスや背景を直接伝えられるようになります。
その場で疑問点をすり合わせたり、画面を見ながら説明できるため、ミスコミュニケーションを防ぎやすくなります。また、口頭で補足することで、資料やメールでは伝えきれない感覚的な部分も共有しやすくなります。
全体の進行がスムーズになるだけでなく、最終的なデザインの満足度も高まる可能性が大きくなります。
やり取りを共有するためにメールのCCに入れる
情報共有を円滑にするためには、デザイナーも含めた関係者全員が同じ情報を持っておくことが大切です。メールのやり取りであれば、WebデザイナーをCCに入れておくことで、経緯や背景が共有されやすくなります。
指示内容の伝達漏れや、細かいニュアンスの食い違いも防げるため、やり取りの正確性が上がります。また、あとから誰が何を言ったかが確認できるため、トラブル時の対応もしやすくなります。
情報がリアルタイムに届く環境をつくることで、制作全体の連携力も高まり、結果として完成までのスピードや品質に好影響を与えます。
まとめ:希望通りのWebデザインを実現するために
Webデザインの完成度を高めるためには、デザイナーとの意思疎通が欠かせません。
目的やターゲットを共有し、希望のイメージや必要な機能を具体的に伝えることで、完成品の満足度は大きく変わってきます。万が一うまく伝わらなかった場合も、依頼書の活用や打ち合わせの工夫でズレを修正することが可能です。ポイントを押さえてやり取りすれば、理想に近いWebサイトを形にすることができます。
伝え方ひとつで、Webデザインの仕上がりは確実に変わります。ぜひ今回ご紹介した内容を実践しながら、納得のいくデザイン制作を進めてください。