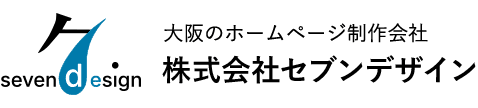- 公開日: 最終更新日:
ホームページに載せる内容とは?必要な情報とメニュー項目の決め方

ホームページを制作する時に、どんな情報を載せるかはとても重要です。伝えたいことだけを並べるのではなく、訪れる人が知りたい情報を整理し、見やすく配置することで成果にもつながります。
このページでは、必要な情報の選び方とメニュー項目の決め方、注意点について解説します。
目次
ホームページに載せる内容とは
ホームページに掲載する内容は、見た目以上に大きな役割を持っています。伝える情報が整理されていないと、訪問者は必要な情報を見つけられず、離脱してしまい、機会損失につながることがあります。
まず考えるべきは、訪れたユーザーが、どんな情報を必要としているかです。会社案内やサービス紹介、料金、実績、問い合わせ方法など、基本的な情報を過不足なく用意することが信頼感につながります。
また、情報の量や順番によって、ユーザーの印象や理解度も変わります。やみくもに情報を載せるのではなく、目的に合わせて中身を絞り込み、分かりやすく配置することが成果に直結します。
ホームページに必要なページの種類
ホームページを構成するページは、業種や目的によって異なります。ただし、必要な情報を整理し、訪問者が迷わず目的を達成できる構成にすることが大切です。ここでは、ホームページに必要なページの種類の考え方について紹介します。
ビジネスに関する情報
まずは、ビジネスに関する情報をしっかりと掲載することが大切です。ただし、すべての情報を盛り込もうとすると、ホームページは複雑で伝わりづらいものになります。サービスや商品に直結する情報に絞り、ビジネスに必要な内容だけを厳選して掲載しましょう。
不要な情報はユーザーの離脱につながるため、何のためにこの情報を載せるのかを明確にしてから選別することが重要です。
ユーザーの知りたい情報
ホームページは自己満足で制作するものではなく、ユーザーの視点で構成する必要があります。訪問者がどんな悩みや目的を持ってページにアクセスしているのかを想像し、それに応える形で情報を設計しましょう。
よくある質問やサービスの強みなど、ユーザーの関心が高い情報から優先的に考えると効率的です。
目的に応じて必要な情報
採用や集客など、ホームページの目的によって必要なページの種類は変わります。目的がはっきりすれば、どのページが必要で、どんな情報を載せるべきかが見えてきます。
ゴールから逆算してページを考えることで、ブレのない構成にすることができます。
コンバージョンに直結する情報
問い合わせや資料請求、見積依頼、電話番号、メールアドレスなど、ユーザーが行動を起こすための情報はホームページに欠かせません。
これらを適切に配置することで、訪問者は迷うことなく行動に移すことができ、成果にもつながります。
ホームページに載せたい基本的な内容
ホームページでは、訪問者の知りたい情報に的確に応えることが重要です。すべてを詰め込むのではなく、必要な情報を整理して見せることで、信頼感や使いやすさにつながります。ここでは、よく掲載されている基本的な内容を紹介します。
商品やサービスに関する内容
自社が提供する商品やサービスは、ホームページにおける最も重要な内容の一つです。
何を提供しているのか、どんな特徴があるのか、誰にとって役立つのかを明確に伝えることで、ユーザーの関心を引き、購入や問い合わせにつながりやすくなります。
あわせて料金プランや導入の流れ、比較表などがあると、より理解しやすくなります。
実績や事例に関する内容
過去の導入事例や取引実績を掲載することで、信頼性や専門性をアピールできます。
写真やお客様の声などを交えることで、実際の成果が具体的に伝わり、初めて訪れるユーザーにも安心感を与える効果があります。BtoBビジネスにおいては特に重要な内容です。
会社情報に関する内容
企業としての基本情報も欠かせません。
会社概要、代表あいさつ、沿革、拠点情報などを整理して掲載することで、どんな会社がホームページを運営しているのかがわかり、ユーザーからの信頼獲得につながります。
取引先が閲覧することも想定し、丁寧に整えましょう。
サポートに関する内容
商品やサービスの利用に関するサポート情報も重要です。
お問い合わせフォームや電話番号、対応時間、よくあるご質問などを用意しておくことで、ユーザーの不安を減らし、信頼感を高められます。
サポート体制がしっかりしている企業は、選ばれる理由の一つになります。
採用に関する内容
採用活動を行っている企業であれば、採用情報ページも重要です。
募集要項や働く環境、社員インタビューなどを通して、自社の魅力を伝えましょう。
求職者は、どんな人が働いているのかや、どんな価値観の会社かがエントリーの判断材料となるため、企業の雰囲気や考え方を伝えることが大切です。
ノウハウや専門性に関する内容
自社の専門知識やノウハウを発信することで、業界内での信頼性や権威性を高めることができます。
コラムやブログ、導入ガイド、チェックリストなど、ユーザーにとって役立つ情報を提供することで、SEOにも貢献するため、集客やブランディングにつながります。
各ページに載せるべき情報の整理方法
ページごとの情報を効果的に整理することで、ユーザーにとって見やすく、理解しやすい構成になります。ここでは、各ページに何を載せるべきかを判断し、適切に整理するための考え方を紹介します。
競合サイトを確認する
まずは、競合サイトを複数チェックし、どのようなページ構成で、どんな情報を掲載しているかを確認します。
特に検索順位が高いホームページを分析することで、検索エンジンにどんな情報が評価されているのか、ユーザーが何を求めているかの内容が見えてきます。
構成や見出しの付け方、使われているコンテンツの種類なども参考になります。
社内で必要なコンテンツを洗い出す
競合を見たうえで、自社の強みやユーザーに伝えるべき情報を整理していきます。
関係者と共有しながら、サービス内容、実績、会社情報、よくあるご質問など、必要と思われる情報をリストアップしていきます。
この段階では、ページ単位にこだわらず、伝えたい内容をもれなく出すことが大切です。
各ページの役割に合わせて情報を振り分ける
リストアップした情報は、どのページに載せるのが適切かを考えながら振り分けていきます。
たとえば、サービスの詳しい説明は、サービス紹介ページ、会社の理念や歴史は会社概要ページなど、各ページの役割と訪問者の期待に合わせて配置します。
情報の重複や過不足がないように調整することがポイントです。
載せる内容に優先順位をつける
すべての情報を同じように扱うのではなく、ユーザーが最も知りたいことを前半に、補足的な内容は後半に回すといった工夫が必要です。
検索エンジンから訪れたユーザーは短時間でそのページが自分にとって価値があるかを判断するため、重要な情報はなるべくページ上部に配置することを意識しましょう。
スマートフォンでの閲覧も考慮するとより効果的です。
読みやすい形で情報を整理する
載せる情報が決まったら、見出し、段落、箇条書き、表などを使って視認性を高めていきます。情報が整理されていないと、どれだけ有益な内容でも読まれません。
さらに、情報量が多すぎるページは、適切にページを分けることで読みやすさが高まります。
文章の構成やレイアウトに気を配りながら、ユーザーがストレスなく読み進められるように整えましょう。
ホームページのメニュー項目の決め方
メニュー項目は、訪問者がサイト内を迷わず移動するための道しるべです。適切な項目名と配置を考えることで、必要な情報にすぐアクセスできるようになり、滞在時間や成果に良い影響を与えます。ここではホームページのメニュー項目の決め方を紹介します。
メニューに載せる情報を洗い出す
まずはサイト全体の情報を整理し、どの情報をメニューに載せるべきかを検討します。訪問者が頻繁にアクセスするページや、集客・問い合わせにつなげたいページは、優先的にメニュー化するのが基本です。
また、サービス紹介、会社情報、採用情報、よくある質問など、ユーザーが求める情報も見落とさずにリストアップしましょう。
グローバルナビとフッターメニューを使い分ける
グローバルナビゲーションは、画面上部に常時表示される主要なメニューで、ユーザーが最初に目にする重要な導線です。一方、フッターメニューはページ下部に配置され、補足的な情報を伝える役割を持ちます。
前のステップで洗い出した情報を、どちらに掲載するかを考えましょう。
ビジネスに直結する重要な内容はグローバルナビに、補足的で優先度の低い内容はフッターメニューに配置することで、構成にメリハリが生まれ、ユーザーが目的の情報にたどり着きやすくなります。
表示する順番を考える
メニューに載せる項目は、ただ並べるのではなく、ユーザーの行動や閲覧の流れを意識して配置することが大切です。左上から順に重要度の高い項目を配置し、スマートフォンの場合は折りたたみメニュー内でも見つけやすい順番を意識しましょう。
メニューの順番は、ユーザーの行動に大きな影響を与える要素です。
ユーザーが迷わないメニュー名にする
メニュー名は、見ただけでどんなページかが想像できる言葉を使うのがポイントです。たとえば、サービス紹介・料金案内・会社概要など、曖昧な表現よりもシンプルで分かりやすい表記を心がけましょう。
専門用語や独自の言い回しは避け、ユーザーの理解を優先した命名が重要です。
ホームページの内容を決める時の注意点
ホームページに載せる内容は、ただ掲載したい情報だけで構成するのではなく、運営面やユーザー体験、成果につながる導線など、いくつかの観点から注意して設計する必要があります。ここでは、内容を決める際に押さえておきたい注意点を紹介します。
スマホでの閲覧を意識した構成にする
近年では、ホームページへのアクセスの多くがスマートフォンから行われています。
そのため、パソコン向けだけでなく、スマホ画面でも読みやすく、操作しやすい構成にすることが重要です。
文字サイズ、行間、ボタンの押しやすさ、スクロールの量など、モバイル環境でのユーザー体験を意識して設計しましょう。
更新や管理のしやすさを考慮する
ホームページは公開して終わりではなく、情報の更新や修正が発生するものです。
運営をスムーズにするには、管理しやすい構成やシステム設計が必要です。たとえば、よく更新する情報はCMSで管理したり、複雑な構成にせずシンプルにまとめることで、誰でも簡単にメンテナンスができます。
SEOとのバランスを意識する
ユーザーにとって分かりやすい構成であることは前提ですが、同時に検索エンジンにとっても理解されやすい構成にすることが重要です。
タイトルや見出し、ページごとのキーワード設計、内部リンクの配置など、SEOを意識した情報整理を行うことで、検索結果での上位表示につながります。
コンバージョン導線を意識する
ホームページの最終目的が、問い合わせや資料請求、購入などのコンバージョンである場合、訪問者が自然とその行動にたどり着けるような導線設計が欠かせません。
たとえば、各ページにお問い合わせボタンを設置する、必要な情報を読んだ直後にコンバージョンポイントを配置するなど、ユーザーの行動を想定した設計が重要です。
まとめ:ホームページに載せる内容を見直して成果につなげよう
ホームページの成果を高めるには、ただ情報を並べるのではなく、目的とユーザーの視点を踏まえて内容を選び、整理することが重要です。必要なページを設計し、それぞれに適した情報を載せることで、分かりやすく信頼感のあるホームページ制作が行えます。
また、メニューの項目も、ユーザーの行動に影響する大切な要素です。内容や導線を見直すことで、ホームページの使いやすさが向上し、問い合わせや購入といった成果につながります。
一度公開した後も定期的に内容を見直し、自社の目的やユーザーニーズに合った構成を保つことが、成果の出るホームページの鍵となります。