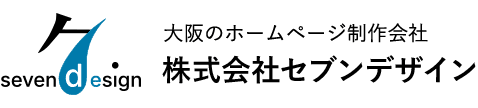- 公開日: 最終更新日:
直帰率とは?計算方法や平均値の目安、GA4での見方、改善策

ホームページの運営において、訪問者の直帰率は重要な指標のひとつです。特に、初めて直帰率を目にしたとき、何を意味しているのだろう?、改善する必要はあるのか?と感じる方も多いのではないでしょうか。
本ページでは、直帰率の基本的な意味や計算方法、業界別や流入経路別の平均値の目安を解説しながら、GA4を使った確認方法や直帰率を改善する具体的な方法をご紹介します。特に、ホームページ制作に携わる方や運営担当者にとって、直帰率を正しく理解し、適切に対策を講じることは、成果向上のために欠かせません。
この記事を通じて、直帰率の仕組みを理解し、ホームページの改善に役立てていただければと思います。
目次
直帰率とは
直帰率とは、訪問者がホームページを訪れた後、他のページを閲覧せずに離脱してしまう割合を指す指標です。直帰率は、訪問者がサイトのコンテンツに満足したか、あるいは求めている情報にたどり着けたかを示す手がかりになります。
直帰率の数値はサイトの種類や目的によって適切な値が異なります。例えば、ECサイトやコーポレートサイトでは複数ページを閲覧してもらうことが重要ですが、ランディングページでは1ページで完結することが多いため、必ずしも直帰率が低いほうが良いとは限りません。
ホームページ制作を行う際には、直帰率をただ下げるのではなく、サイトの目的や訪問者の行動を考慮した上で、この指標を評価することが大切です。
直帰率の計算方法
直帰率とは、ホームページを訪れたユーザーのうち、他のページを閲覧せずにそのまま離脱した割合を指しています。計算方法は以下の通りです。
直帰率(%)= 直帰数 ÷ 入口回数 × 100
- 直帰数:特定のページに訪問し、他のページを閲覧せずに離脱した回数
- 入口回数:そのページが訪問者にとって最初に表示された回数
例えば、あるホームページの特定ページで、入口回数が100回あり、そのうち50回が直帰数の場合、直帰率は次のように計算されます。
直帰率= 50 ÷ 100 × 100 = 50%
この計算によって、訪問者がページ内でどのような行動を行ったかを簡単に把握できます。ホームページ制作では、直帰率を通じてページの効果を評価し、デザインやコンテンツの改善ポイントを見つけることが重要です。
直帰率の平均値の目安
直帰率の平均値は、必ずしも自社サイトの評価基準として参考になるとは限りませんが、目安を知りたいと考える方も多いでしょう。当社では感覚的に50%弱程度が平均的な数値だと考えていますが、具体的なデータを基にした比較を希望される場合もあるかと思います。
そこで、海外のホームページBounce Rate Benchmarks: What’s a Good Bounce Rate, Anyway?に掲載されている直帰率の平均値をご紹介します。
業界別
業界別の平均直帰率は以下の通りです。
| 飲食 | 65.52% |
| ニュース | 56.52% |
| 美容とフィットネス | 55.73% |
| コンピューターと電子機器 | 55.54% |
| インターネット | 53.59% |
| ファイナンス | 51.71% |
| スポーツ | 51.12% |
| 旅行 | 50.65% |
| ビジネスと産業 | 50.59% |
| 不動産 | 44.50% |
業種ごとの直帰率は、サイトの目的によって異なります。
例えば、飲食業界ではアクセスマップや営業時間の確認といった1ページで完結する情報が多く、高い直帰率が一般的です。一方、不動産や旅行関連のサイトでは、比較検討を行うユーザーが多いため、直帰率が若干低めになる傾向があります。
ただし、これらの業種でもページの内容がユーザーの期待に応えられていない場合、改善が必要となることがあります。いずれの業種においても、直帰率が高いか低いかだけでは成果を判断できません。訪問者の意図や、直帰前の行動を含めて総合的に評価することが重要です。
流入経路別
流入経路別の平均直帰率は以下の通りです。
| ディスプレイ広告・バナー広告 | 56.50% |
| SNS | 54.00% |
| ダイレクトアクセス(URLの直打ちやお気に入り) | 49.90% |
| リスティング広告・検索連動型広告 | 44.10% |
| 検索エンジンの検索結果 | 43.60% |
| 別サイトからのリンク | 37.50% |
| メール(メールマガジン) | 35.20% |
流入経路によって直帰率が大きく異なる理由は、訪問者の意図に起因します。
たとえば、ディスプレイ広告やバナー広告からの流入では、興味本位でのクリックが多いため直帰率が高くなりがちです。一方、検索エンジンの検索結果やメール経由では、訪問者の目的意識が強いため直帰率が低くなる傾向があります。
これらの傾向を把握し、改善ポイントを見極めることが重要です。
直帰率は低いほうがいいのか
直帰率は一般的に低いほうが良いとされていますが、それはすべてのケースに当てはまるわけではありません。直帰率が高いことが必ずしも問題というわけではなく、ページの目的や訪問者の意図によって、その評価基準は異なります。
たとえば、商品・サービスや実績・事例ページのように、訪問者に詳しい情報を提供したり、次の行動を促すことが目的のページでは、直帰率が低いほうが望ましいと言えます。一方で、アクセスマップや営業時間の案内など、1ページで完結する情報を提供するページでは、直帰率が高いのは自然なことです。
このような場合、直帰率が高くても訪問者の目的が達成されていれば問題ありません。直帰率を正しく評価するには、訪問者が直帰する前の行動を分析し、ページの役割や成果に基づいて判断することが重要です。
ページごとに理想的な直帰率を設定し、適切な改善施策を講じることで、サイト全体のパフォーマンスを向上させることが可能になります。
直帰率が高くなる原因
直帰率が高いと、訪問したユーザーがすぐにサイトを離れてしまい、成果につながりにくくなります。ここでは、直帰率が高くなる原因について解説します。
コンテンツがユーザーニーズと合っていない
ユーザーが求めている情報とページの内容が一致していないと、直帰率が高くなりやすくなります。特に、検索結果や広告を見てアクセスしたユーザーが、期待していた情報を得られなかった場合、すぐに離脱する可能性が高くなります。
例えば、タイトルやメタディスクリプションの内容と実際のコンテンツにズレがあると、ユーザーはページを開いた瞬間に違和感を覚え、すぐに離れてしまいます。また、SNSなどのリンク経由で訪れた場合も、表示されていた内容と実際のページが異なると、信頼を損ねる原因になります。
ユーザーの検索意図を正しく把握し、タイトル・ディスクリプション・ページの内容を一貫性のあるものにすることで、直帰率の低減につながります。
スマホの表示速度やレイアウト崩れ
スマホでのページ表示速度が遅いと、ユーザーはページが開く前に離脱してしまいます。特にモバイルユーザーは、PCよりも短時間で情報を取得しようとするため、ページの読み込みが遅いと直帰率が大幅に上がる傾向にあります。
また、スマホでのレイアウト崩れも直帰率の原因の一つです。画面の幅に適していないデザインや、タップしづらいボタン配置だと、ユーザーはストレスを感じてページを離れてしまいます。モバイル最適化を意識し、表示速度の改善やレスポンシブデザインの調整を行うことが重要です。
内部リンクがないと回遊しづらい
サイト内に適切な内部リンクが設置されていないと、ユーザーが次にどのページを見ればよいのか分からず、直帰しやすくなります。
特に、ブログ記事の場合、関連するページへスムーズに誘導することが重要です。例えば、この内容についてもっと詳しく知りたいと思っても、適切なリンクがなければ、ユーザーは別のサイトを探しにいってしまいます。
サイト内の回遊率を上げるためには、適切な位置に関連ページへのリンクを設置し、ユーザーの行動を促すことが大切です。
GA4で直帰率を確認する方法
GA4では、直帰率の定義が上記で紹介した従来の考え方とは異なります。GA4での直帰率は、エンゲージメントが発生しなかったセッションの割合を指します。従来の1ページだけを閲覧して離脱したセッションを直帰とみなす定義とは異なり、GA4ではユーザーの行動をより詳細に反映する形に変更されています。
では、GA4で直帰率を確認する方法を紹介します。
- ページとスクリーンレポートを開く
GA4のナビゲーションメニューからレポート→エンゲージメント→ページとスクリーンを選択します。 - レポートをカスタマイズする
画面右上の鉛筆アイコンをクリックしてカスタマイズ画面を開きます。 - 直帰率を追加する
指標を追加をクリックしてリストから直帰率を選択して適用をクリックします。 - カスタマイズしたレポートを保存する
保存を選択して既存レポートの上書きか新しいレポートとして保存します。 - 保存したレポートを確認する
保存したレポートはレポート→ライブラリからアクセスできます。
GA4で直帰率を確認することで、訪問者がどのように行動しているかを把握でき、サイトのパフォーマンス改善に役立てることができます。
GA4の定義を理解し、適切に活用することで、訪問者のニーズに合ったサイト運営を実現することが可能です。
直帰率の改善策
直帰率が高いページには改善の余地があります。しかし、闇雲に対策を行うのではなく、問題点を特定し、効果的な順序で改善を進めることが重要です。以下のステップを参考にしながら、効率的に直帰率を下げるための具体的な方法を実施しましょう。
1. 改善すべきページを発見する
直帰率を改善する第一歩は、直帰率が特に高いページを特定し、それが問題かどうかを評価することです。
GA4や他のアクセス解析ツールを使用して直帰率の高いページを確認します。その際に、直帰率が高いことがページの目的に照らして問題であるかどうかを判断することが重要です。
例えば、アクセスマップや営業時間を掲載するページなど、1ページで訪問者の目的が完結する場合は、直帰率が高くても問題はありません。一方、商品や実績・事例ページなど、複数ページを閲覧してもらうことが期待されるページで直帰率が高い場合は、訪問者のニーズを満たせていない可能性があります。
どの部分が改善を必要としているのかを詳細に分析し、次のステップにつなげていきましょう。
2. サイトの表示速度を改善する
ページの表示速度が遅いと、訪問者がページを開く前に離脱してしまう可能性が高まります。
特にスマートフォンからのアクセスが多い場合は、表示速度は直帰率に大きく影響します。GoogleのPageSpeed Insightsなどのツールを活用し、改善ポイントを把握しましょう。
具体的には、画像の圧縮、キャッシュの有効活用、不要なスクリプトの削除などが挙げられます。表示速度を改善することで、訪問者がストレスなくページを閲覧できるようになります。
3. 内部リンクを設置する
訪問者が次のページに進むきっかけを作るために、内部リンクを適切に配置します。例えば、記事の最後に関連ページのリンクを設けたり、商品説明ページ内に関連記事やお客様の声へのリンクを設置することで、ページ間の導線を強化できます。
次に読むべき内容を明確に提示することで、訪問者が1ページだけで離脱する可能性を減らすことができます。
4. タイトルとディスクリプションを改善する
検索結果からのクリックを誘導するためのタイトルやディスクリプションが、実際のページの内容と一致していない場合、訪問者がすぐに離脱してしまうことがあります。
検索意図を理解し、訪問者が期待する情報を端的に伝えるタイトルやディスクリプションに改善しましょう。特に、内容を誇張したり曖昧にするのではなく、具体的でわかりやすい表現を心がけることが重要です。
5. コンテンツを改善する
ページの内容が訪問者の検索意図に合致していない場合、直帰率が高くなる傾向があります。具体的には、訪問者が探している情報が十分に網羅されていない、またはわかりにくい場合です。
ページの目的を見直し、ターゲットとする読者にとって価値のある情報を追加したり、見やすいレイアウトに変更するなどの工夫を行いましょう。
6. デザインを一新する
デザインが古い、使いづらい、または視覚的に魅力がない場合も、訪問者は早々に離脱することがあります。特に、スマートフォンでの表示が最適化されていない場合は、デザインを見直す必要があります。
視覚的な要素を強化するだけでなく、ユーザーの操作をスムーズにする導線設計を考慮することが重要です。
まとめ:直帰率の改善はホームページの成果向上に必須
直帰率は、訪問者がサイトのコンテンツにどれだけ満足しているかを示す重要な指標です。しかし、直帰率が高いことが必ずしも問題というわけではなく、ページの目的や訪問者の意図に応じた評価が必要です。
GA4でのデータ分析や、表示速度の改善、内部リンクの活用など、具体的な施策を順序立てて実行することで、直帰率の改善につながります。これにより、訪問者がサイト内で次のアクションを起こしやすくなり、ホームページの成果向上にも大きく影響します。
直帰率を正しく理解し、効果的な改善を行うことで、サイト運営の効率化と目標達成に近づけるでしょう。
また、直帰率を深く理解するためには、離脱率との違いを知ることが大切です。詳しくは離脱率と直帰率の違いのページをご覧ください。