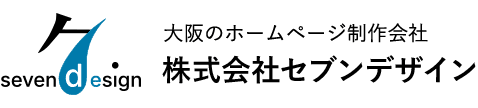- 公開日: 最終更新日:
PDCAとは?サイクルの回し方とWebサイト改善のポイント

Webサイトの改善には、現状分析から施策の実行、効果測定、そして改善まで、一連の流れを繰り返すことが欠かせません。そのプロセスを体系的に整理し、効率的に進めるためのフレームワークがPDCAサイクルです。
本記事では、PDCAの基本やWebサイト改善への活用方法を軸に、Webマーケティングで活用されるPDCAサイクルの種類についても紹介します。
目次
PDCAとは
PDCAとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の頭文字をとった業務改善や品質管理の現場で広く使われているフレームワークです。この4つのステップを繰り返し行うことで、業務の最適化や成果の最大化を図ることができます。
もともとは製造業や品質管理の分野で取り入れられてきた手法ですが、現在ではWebサイトの運用やWebマーケティング施策、広告運用、SNS発信、SEO対策といった分野にまで広く応用されています。
PDCAという言葉が注目されるようになった背景には、Web上での施策が一度きりで終わるものではなく、継続的な改善を前提に成り立っているという特性があるからです。
たとえば、Webサイトのリニューアルを行ったとしても、公開後に何の検証も行わず放置してしまえば、成果につながらない可能性があります。そこで重要になるのが、PDCAサイクルを通じて、現状を分析し、改善を重ねていくプロセスです。
こうした継続的な改善活動を前提とするPDCAサイクルの考え方を取り入れることで、ページの質やユーザー体験の向上、成果の最大化といった目標がより現実的なものになります。
Webサイトの改善点の見つけ方がわからない、施策の結果が出ない、何を基準に改善すればいいのかわからないといった悩みを抱える担当者にとって、PDCAは非常に有効なアプローチと言えるでしょう。
PDCAサイクルの流れ
PDCAサイクルを使ったWebサイトの改善においては、ただ実行するだけでは成果につながりません。重要なのは、一つひとつの施策を検証し、改善につなげるサイクル思考です。ここでは、PDCAサイクルを構成する4つのステップを、それぞれの役割やポイントとあわせて解説します。
Plan(計画)
Planでは、Webサイトの課題を洗い出し、どのような改善が必要かを検討します。ただ施策を実行するのではなく、なぜ成果が出ていないのか?という原因を見極めることが重要です。
まずは、目標を明確に設定します。たとえば、お問い合わせ件数を月10件増やすといった具体的なゴールを定め、その達成に向けた課題の洗い出しを行います。
Googleアナリティクスやヒートマップなどの分析ツールを使ってユーザー行動を確認すれば、現状と理想のギャップが明確になり、どこに改善の余地があるのかが見えてきます。
こうした分析をもとに施策の計画を立てることで、より効果的な改善が可能になります。
Do(実行)
計画した施策を、実際にWebサイト上で実行するステップです。たとえば、ページの構成を変えたり、導線を改善したり、キャッチコピーやボタン配置を見直すなど、具体的な作業がここにあたります。
実行にあたっては、誰が・いつまでに・どのように行うかといった実務レベルの段取りも整理しておくと、スムーズに進められます。この段階では、まだ改善効果が出るかどうかは分かりません。大切なのは、仮説に基づいた施策を丁寧に実行することです。
Check(評価)
施策を実行したあとは、どのような結果が出たのかを確認し、冷静に評価を行います。重要なのは、単に成果が出た・出なかったを見るだけでなく、なぜその結果になったのか?という背景を分析することです。
たとえば、アクセス解析やヒートマップツールを使えば、ページの滞在時間や離脱率、ユーザーのクリック位置などから、ユーザー行動の変化を把握できます。こうした定量データとあわせて、ユーザーの動きといった定性的な情報も確認することで、より深い気づきや次の改善につながるヒントが得られるでしょう。
Action(改善)
Checkで得られた評価結果をもとに、明確に浮かび上がった課題に対して、実際の改善施策を行うフェーズです。たとえば、検索順位が想定より低ければコンテンツのリライトや構成変更、CVRが伸び悩んでいる場合にはCTAの見直しや導線の修正など、評価で見えた問題点に応じた対応を行います。
ここで重要なのは、分析しただけで終わらせず、数値の変化やユーザーの行動に基づいて、改善策を実行に移すことです。改善の質が次のPlanの精度にも影響するため、この段階で得た知見は次のサイクルにしっかり反映させましょう。
PDCAサイクルを使ったWebサイト改善のポイント
PDCAサイクルを効果的に活用するには、単に回すだけでは不十分です。重要なのは、PDCAの各ステップに入る前の準備と、サイクルを続けるための仕組みづくりです。ここでは、PDCAサイクルで押さえるべき改善ポイントを紹介します。
PDCAサイクルを実施する前に分析を徹底する
PDCAサイクルを始める前に、Webサイトの現状を正確に把握することが何よりも重要です。改善すべきポイントが曖昧なままでは、適切な施策を立てられず、PDCAの精度も下がってしまいます。
具体的には、ヒートマップやアクセス解析ツールを用いて、ユーザーの行動パターンを可視化しましょう。さらに、ヒューリスティック分析やユーザビリティテストも組み合わせることで、定性的・定量的な両面からサイトの改善点を見つける精度が高まります。
事前分析をしっかりと行うことが、課題の本質を見抜き、的確な施策へとつなげる土台になります。
KPIやKGIをPDCAに活用する
PDCAにおけるサイト改善では、KPIやKGIの設定が欠かせません。KGIとそれに紐づく複数のKPIを活用することで、PDCAサイクルの進捗と成果を数値で捉えられるようになります。
たとえば、ECサイトの売上10%アップというKGIを掲げた場合、SNSフォロワーを1万人増やすやLPのCVRを2%改善するなど、具体的なKPIを設定しましょう。そして、それぞれのKPIに対して個別にPDCAを回すことで、施策の有効性やボトルネックの特定が容易になります。
また、設定するKPIは一つに絞らず、多角的に洗い出すことが重要です。すべてを管理・分析する必要はありませんが、達成率が低い指標だけをピックアップしてモニタリングすることで、効率よくPDCAを回せます。
1年以上のスケジュールを立てる
PDCAでは、1回のサイクルで大きな成果を出すことよりも、何度も回して改善精度を高めることが求められます。そのため、あらかじめ中長期的な計画を立てておくことが成功の鍵です。
たとえば、1サイクル=4ヶ月を基準に、年間で3サイクルを回すといったスケジュールを設定すると、目標設定・検証・改善のサイクルが継続的に機能します。改善活動に一貫性を持たせることで、PDCAサイクルが形式的なものに終わらず、実際の成果に結びつきやすくなります。
継続的にPDCAを回す体制を整えることが、Webサイトの改善やチーム全体の成長につながるでしょう。
PDCAが回せない時の原因と解決策
Webサイトの改善にPDCAサイクルを取り入れても、期待した成果が出ず、改善につながらないケースは少なくありません。PDCAが正しく機能しない原因は複数あり、それぞれに対して適切な対処が求められます。ここでは、PDCAサイクルでつまずきやすいポイントと解決策を解説します。
KPIの設定が不十分
PDCAサイクルを使ったWebサイトの改善でつまずきやすい原因のひとつが、KPIの設定不足です。たとえば、売上アップや問い合わせを増やすといった抽象的な目標しかない場合、何を基準に成功とするのかが曖昧になり、施策の評価や改善が難しくなります。
まずは、業界の平均値や実績データをもとに、リード獲得数やCVRなど、定量的なKPIを仮設定しましょう。
たとえ仮の数値であっても、PDCAを回す中でCheckの段階で効果を確認し、数値が高すぎたり低すぎたりすれば、柔軟に調整すれば問題ありません。
特にBtoBサイトでは、受注数から逆算してWeb流入数やコンバージョン数を割り出す方法が有効です。KPIを明確にすることで、PDCAとして改善すべき課題が可視化され、次の施策も明確になります。
CheckやActionを行わない
PDCAのCheckやActionが機能していないのも、よくある失敗パターンです。施策を実行したあとに結果の分析をせずに終えてしまったり、分析はしたものの改善策が定まらず、同じ施策を繰り返してしまったりといったケースが該当します。
これを防ぐには、定期的な振り返りと改善を行うミーティングを設けるのがおすすめです。施策の担当者が、何をして、どんな結果が出て、どのように改善すべきかを共有することで、PDCAサイクルの改善精度が飛躍的に高まります。
また、責任の所在を明確にし、誰が次のアクションを取るのかを決めておくことも重要です。
効果測定ができない
PDCAを回したくても、施策の効果が測定できなければ改善のしようがありません。Googleアナリティクスやヒートマップツールを導入していても、使いこなせていない場合は意味がありません。
そもそもどの数値を見れば改善点が分かるのか分からないといった悩みを持つ方も多いです。これはスキル不足に起因するケースが多く、社内でのスキルアップや外部支援の活用が必要です。
たとえば、データ分析スキルを高めるためにオンライン講座を受講したり、外部のWebコンサルティング会社に伴走してもらうことで、PDCAサイクルとしてのサイト改善がスムーズに進むようになります。
改善サイクルの質を高めるには、効果測定のノウハウを持つ人材やサポートの導入が有効です。
WebマーケティングにおけるPDCAの種類
Webサイトを改善して成果を出すには、目的や媒体に応じたPDCAサイクルの使い分けが欠かせません。ここでは、WebマーケティングにおけるPDCAの種類を紹介します。
SEO対策のPDCAサイクル
SEO対策におけるPDCAでは、検索ユーザーの意図を深く読み取り、それに合ったコンテンツ設計と改善を継続することが重要です。特に、PDCAサイクルで成果を出すには、それぞれのフェーズを明確に意識して運用することが不可欠です。
Planでは、まずターゲットユーザーの悩みや検索ニーズを分析し、それに基づいたキーワードを選定します。
想定される検索キーワードを洗い出し、そのキーワードに対して提供すべき情報やページ構成、見出し設計、タイトル案などを計画します。また、上位表示を狙う競合コンテンツの構成や内容も参考にし、差別化ポイントを設計段階で検討しておくことが効果的です。
Doでは、Planで設計した構成やコンテンツ方針に沿って実際のページを制作します。
記事やサービス紹介ページ、コラムなどのコンテンツを作成・公開し、Googleにインデックスされるようにサーチコンソールで登録します。あわせて、タイトルタグやディスクリプション、内部リンク設計などもSEOに最適化された形で反映しておきます。
Checkでは、検索順位やクリック率、流入数、コンバージョン率などのデータをもとに、狙ったキーワードでどの程度成果が出ているかを確認します。
GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスを使い、ページごとのパフォーマンスをチェックします。順位が上がっているか、ユーザーが期待通りにページを閲覧しているか、離脱率は高くないかなど、詳細に分析して現状を把握することがポイントです。
Actionでは、Checkで得られたデータをもとに改善を実行します。たとえば、順位が想定より低い場合は、記事の追記・リライト・構成変更などのSEOリライトを行い、検索意図とのズレを修正します。逆に順位が高くてもCVRが低い場合は、導線の改善やCTAの見直しが必要です。
また、成果が頭打ちのキーワードであれば、新しい関連キーワードへの展開を検討し、新規コンテンツの追加という形で次のPlanにつなげるのも有効です。
SEO対策は一度の施策で終わるものではなく、検索アルゴリズムの変化や競合コンテンツの更新に応じて繰り返し改善が必要です。PDCAサイクルとして機能させるためには、四半期単位でPDCAを継続的に回し、ページを育てていく視点が求められます。
コンテンツマーケティングのPDCAサイクル
コンテンツマーケティングでは、ユーザーの課題を起点にしたコンテンツの最適化と、届け方の精度が成果を左右します。PDCAで成果を出すには、読み手の行動を促す構成と改善サイクルの継続が重要です。
Planでは、ペルソナやカスタマージャーニーをもとに、ユーザーがどのタイミングで何に困っているかを整理し、それに応じたコンテンツの方向性を設計します。自社にある既存記事やホワイトペーパー、事例などの情報を棚卸しし、不足しているテーマやリライトが必要な箇所を洗い出します。
Doでは、ターゲットが知りたい内容をわかりやすく、行動につながるよう設計されたコンテンツを制作します。構成案をもとに文章や画像を用意し、誰に・何を伝え・どんなアクションを促すのかを明確にして配信するのがポイントです。
Checkでは、Googleアナリティクスやヒートマップツールを用い、UU・PV・離脱率・ページ滞在時間などの定量データからユーザー行動を可視化します。想定した導線どおりに動いているか、どこで離脱しているのかを確認し、数値に基づいた課題の洗い出しを行います。
Actionでは、分析データをもとに課題となる箇所をリライトしたり、CTAやコンテンツの構成を変更するなどの改善を加えます。コンテンツの目的は読まれることではなく行動を促すことであり、その成果に直結する要素を中心に改善施策を練り、次のPlanにつなげます。
SNS運用のPDCAサイクル
SNSはスピード感と継続性が求められるメディアであり、PDCAもテンポよく回す必要があります。PDCAでSNS経由のトラフィックや認知拡大を狙うには、ターゲットに響く投稿とタイムリーな改善が重要です。
Planでは、運用目的を明確にし、どのSNSでどんなテーマの投稿をどの頻度で行うかを計画します。媒体の特性を考慮しながら、投稿の内容・トーン・ビジュアル方針を事前に整理しておきます。
Doでは、計画に基づいて投稿を行います。画像や動画、文章の表現を工夫し、ターゲットユーザーにとって価値ある情報を届けるとともに、コメントやDMにも丁寧に対応することでコミュニケーションを強化します。
Checkでは、いいね・コメント・シェア・エンゲージメント率・フォロワー数など、SNS独自の指標をもとに反応を分析します。どの投稿にどんな反応があったか、曜日や時間帯による効果の違いなどを数値で確認し、改善点を洗い出します。
Actionでは、投稿内容・投稿頻度・ハッシュタグなどを見直し、成果が出やすいパターンに寄せて運用を調整します。また、反応の良かった投稿パターンをテンプレート化し、他媒体へ横展開するのも効果的です。
ユーザーとの関係構築を深めながらPDCAを継続し、ブランドのファン化と流入増加を図ります。
Web広告のPDCAサイクル
Web広告は短期間で結果が見える分、迅速な改善が求められる施策です。PDCAにおいても、広告流入の質とコンバージョンの最適化を支える重要なチャネルとなります。
Planでは、まず広告の目的とターゲットを明確にし、訴求すべき強みや競合との違いを洗い出します。その上で、ターゲットが多く利用する媒体を選定し、配信する広告の内容や予算、KPIを設定します。
Doでは、広告文やバナーを制作し、ランディングページとセットで出稿します。LPには、ユーザーの悩み→解決策→行動喚起という構成を意識して情報を掲載し、初見でもすぐに魅力が伝わるように設計します。
Checkでは、コンバージョン件数やコンバージョン単価、クリック率、広告表示回数などを分析します。成果が出ていない場合は、広告とランディングページのどこにボトルネックがあるかを分解して特定します。
Actionでは、成果の悪い広告文を差し替えたり、ランディングページのファーストビューを改善したりといった具体的な施策を実施します。また、媒体や配信ターゲットの見直しを行うことで、より費用対効果の高い広告運用に繋げていきます。
Web広告は2~3日単位で効果が可視化されるため、週次でPDCAを回すのが理想です。
PDCAのまとめ
PDCAとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)の4つのステップを繰り返すことで、業務や施策の質を高めていく改善手法です。これは製造業やビジネス全般で用いられてきた考え方ですが、Webサイトの改善や運用にも非常に相性が良いフレームワークです。
実際のWebサイト改善では、ヒートマップやアクセス解析、ユーザビリティテストといったツールを使いながら現状を分析し、KPIに沿って施策を設計、実行します。その結果をもとに振り返り、必要に応じてコンテンツや導線の見直しを行っていきます。
こうしたPDCAサイクルを継続的に実施できるWebサイトは、一度きりで終わらず、成長を続けられる構造を持っていると言えます。近年では、このように改善前提で運用されるサイトを重視する企業も増えてきました。
成果を出すには、KPI設計や改善体制を整え、1回で終わらずに中長期的な視点でサイトを育てていくことが重要です。PDCAをしっかり回し続けることが、Webサイトの成果向上につながります。
なお、本ページの作成にあたっては、PDCAサイクルを早く回す7つのコツ!基本的な回し方や具体例も解説|Siteleadの内容を参考にしています。PDCAをよりスピーディーに回すための具体的なコツが紹介されているので、あわせて参考にしてみてください。