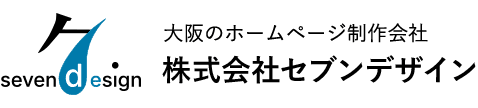- 公開日: 最終更新日:
レスポンシブデザインとは?メリットとデメリット、作り方

スマートフォンやタブレットの普及により、ホームページ制作ではレスポンシブデザインが主流となっています。PCやスマホなど異なるデバイスでも快適に閲覧できるため、多くのサイトで導入されています。
このページでは、レスポンシブデザインの基本やメリット・デメリット、作り方のコツを解説します。導入時の注意点にも触れながら、どのように取り入れるべきかを紹介します。レスポンシブデザインについて知りたい方、どのように作ればいいのか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
目次
レスポンシブデザインとは
レスポンシブデザインとは、閲覧するデバイスの画面サイズに応じて自動的にレイアウトを調整するデザイン手法です。PC、スマートフォン、タブレットなど、異なるデバイスでも一つのウェブサイトを適切に表示できるように設計されています。
従来は、PC版とスマホ版のウェブサイトを別々に作成する方法が一般的でしたが、デバイスの多様化に伴い、1つのウェブサイトで複数のデバイスに対応できるレスポンシブデザインが主流となっています。
レスポンシブデザインを取り入れることで、ユーザーの利便性が向上し、サイトの管理負担を軽減できるため、ホームページ制作において重要な要素の一つとされています。
レスポンシブデザインのメリット
レスポンシブデザインには、ユーザーの利便性向上や管理のしやすさなど、多くのメリットがあります。ここでは、メリットについて解説します。
検索エンジンで上位表示されやすくなる
レスポンシブデザインは、Googleが推奨するウェブデザインの1つです。
レスポンシブデザインを採用することで、PCとスマホで同じURL・HTML構造を維持できるため、検索エンジンの評価が統一され、検索順位が向上しやすくなります。また、ページの読み込み速度を最適化しやすく、ユーザーの離脱を防ぐことで、結果的に検索順位向上につながる要素となります。
SNSでシェアされやすくなる
レスポンシブデザインを採用すると、PCとスマホで同じURLを使用できるため、どのデバイスからアクセスしても適切にコンテンツが表示されます。
そのため、SNSでシェアされたページが、閲覧するユーザーのデバイスに関係なく最適なレイアウトで表示され、読みやすさが維持されます。閲覧ストレスが少ないことで、シェアされやすくなるのもメリットです。
サイトの更新が楽
レスポンシブデザインはPCとスマホ版を別々に管理する必要がなく、1つのHTMLファイルを更新するだけで済みます。これにより、運用負担が軽減され、メンテナンスが効率的に行えるのが大きなメリットです。
また、デザインの変更も一元管理できるため、ホームページの更新がしやすくなります。特に、頻繁にコンテンツを更新するサイトでは、レスポンシブデザインを導入することで作業時間の短縮につながります。
レスポンシブデザインのデメリット
レスポンシブデザインには多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。ここでは、レスポンシブデザインのデメリットについて解説します。
デザインに制限がかかる
レスポンシブデザインでは、PCとスマホで同じHTML構造を使用するため、デザインの自由度が低くなります。
特に、PC向けにリッチなレイアウトを採用したい場合、スマホ表示の最適化とのバランスを取るのが難しくなることがあります。例えば、PCでは横幅を活かしたデザインを取り入れられますが、スマホでは縦スクロールが主体となるため、一部のレイアウトやコンテンツの見せ方に制限が生じる場合があります。
表示速度が遅くなることがある
レスポンシブデザインでは、PC・スマホで共通のHTMLとCSSを使用するため、不要なデータが読み込まれ、スマホの表示速度が遅くなる可能性があります。
特に、高解像度の画像をそのまま使用すると、スマホでは無駄なデータの読み込みが発生し、表示の遅延につながります。さらに、CSSやJavaScriptの読み込みが増えることで、サイトのパフォーマンスに影響を与えることもあります。
レスポンシブデザインの種類
レスポンシブデザインにはさまざまな種類があり、それぞれの手法によってレイアウトの柔軟性や適用範囲が異なります。どの手法を選ぶかは、サイトの目的やデザインの自由度、管理のしやすさなどを考慮することが重要です。ここでは、代表的なレスポンシブデザインの種類について解説します。
レスポンシブレイアウト
レスポンシブレイアウトは、CSSのメディアクエリを利用してデバイスの画面サイズに応じたスタイルを適用する手法です。デバイスの横幅を基準にして、適切なレイアウトを表示するため、PC・スマホ・タブレットなどの異なる環境でも一つのHTMLで対応可能です。
レスポンシブレイアウトは、現在のホームページ制作では一般的な方法となっており、多くの企業サイトやブログで採用されています。ただし、デザインの自由度が多少制限されるため、画面サイズごとに適切な調整を行うことが重要です。
リキッドレイアウト
リキッドレイアウトは、画面サイズに応じてコンテンツの幅が可変するデザイン手法です。パーセンテージで幅を指定することが多く、デバイスの横幅に合わせてコンテンツが自動的に調整されるのが特徴です。
リキッドレイアウトは、柔軟にレイアウトを変更できるメリットがある反面、極端に大きな画面や小さな画面での表示バランスを考慮する必要があるため、デザイン設計の際には慎重な調整が求められます。
フレキシブルレイアウト
フレキシブルレイアウトは、リキッドレイアウトの概念を取り入れつつ、ブレイクポイントを設定してデザインの最適化を図る手法です。単なるリキッドレイアウトでは意図しない崩れが発生しやすいため、CSSのメディアクエリを活用し、特定の画面サイズでレイアウトを調整することで、より柔軟なデザインが可能になります。
フレキシブルレイアウトは、レスポンシブデザインの中でも最適化しやすく、PC・スマホ・タブレットのすべてのデバイスでバランスの取れた表示ができるため、多くのサイトで採用されています。
グリッドレイアウト
グリッドレイアウトは、CSSグリッドやフレックスボックスを活用し、要素を整列させる手法です。画面サイズに応じて列の数や幅を動的に変更することができるため、デザインの一貫性を保ちつつ、柔軟なレイアウトを実現できるのが特徴です。
グリッドレイアウトは、特にデザイン性を重視したサイトや、複数のコンテンツブロックを配置する必要があるサイトに適しています。ただし、設計の段階で適切なブレイクポイントを設定しないと、意図しないレイアウト崩れが発生する可能性があるため注意が必要です。
レスポンシブデザインの作り方のコツ
レスポンシブデザインを適切に設計するには、デバイスごとの表示や動作を考慮しながら、設計・コーディングを進めることが重要です。ここでは、レスポンシブデザインを作る際のコツを解説します。
1. ターゲットの利用端末を検討する
レスポンシブデザインを設計する際は、ターゲットとなるユーザーがどのデバイスを使用するのかを明確にすることが重要です。サイトの種類や目的によって、最適なデバイスの優先度は異なります。
例えば、BtoB向けのサイトでは、業務での利用が多いため、PCでの閲覧が中心になります。そのため、デスクトップ環境を重視しつつ、スマホでも問題なく閲覧できるように設計する必要があります。
一方、ECサイトでは、スマートフォンを利用するユーザーの割合が高くなります。そのため、モバイル表示を最優先に考え、タップしやすいボタン配置や、縦スクロールに適したレイアウトが求められます。
ターゲットの利用端末を事前に分析することで、どのデバイスを中心に最適化すべきかが明確になり、無駄な設計を省くことができます。
2. ブレイクポイントを定める
ブレイクポイントとは、異なるデバイスで最適なレイアウトを適用するために設ける基準となる画面幅のポイントです。適切なブレイクポイントを定めることで、スマートフォン・タブレット・PCそれぞれで最適な表示を実現し、レイアウト崩れを防ぐことができます。一般的なブレイクポイントの基準は以下の通りです。
- スマートフォン:375px〜428px
- タブレット:768px〜960px
- PC:960px〜1280px
スマートフォンでは縦長の表示を重視し、タブレットではコンテンツを広めに配置、PCでは大画面に適したレイアウトを適用する必要があります。
ブレイクポイントの設定は、サイトのターゲットユーザーやコンテンツの特性によって最適な幅を選ぶことが重要です。適切なブレイクポイントを定めることで、どのデバイスでも統一感のあるデザインを維持し、ユーザーの操作性を向上させることができます。
3. デバイスごとのワイヤーフレームとデザインを作成する
ワイヤーフレームとは、ページの構成や要素の配置を決める設計図のことです。レスポンシブデザインを適用する際は、スマートフォン・タブレット・PCの各デバイスごとにワイヤーフレームを作成し、異なる画面サイズでもスムーズに操作できるデザインを考えることが重要です。
| スマートフォン | 縦スクロールなので、シンプルなUIを採用して、直感的に操作できるデザインを意識する |
| PC | 横幅を活かしたレイアウトを検討し、情報を整理しながら視認性を向上させる |
| タブレット | PCとスマホの中間的なデザインを考慮し、違和感のないレイアウトを設計する |
ワイヤーフレームが完成したら、次にデザイン作成に進みます。ワイヤーフレームをもとに、各デバイスで最適な配色・フォントサイズ・余白を調整し、統一感のあるデザインを仕上げることが重要です。
4. HTMLにviewportを記述する
レスポンシブデザインを適用するためには、HTMLの<head>内にviewportを設定する必要があります。これにより、デバイスの画面幅に応じた適切な表示が可能になります。
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
この記述を入れることで、スマホやタブレットでも適切なサイズでコンテンツが表示されるようになります。
5. CSSにブレイクポイントやメディアクエリを記述する
レスポンシブデザインを適用するには、CSSのメディアクエリを活用し、画面サイズごとに適切なスタイルを設定することが重要です。これにより、スマートフォン・タブレット・PCそれぞれのデバイスで最適なデザインを維持できます。
例えば、スマートフォンではフォントサイズを小さく調整し、PCでは読みやすいように大きめのフォントサイズを適用する場合、以下のようにメディアクエリを使用します。
body {
font-size: 16px;
}
@media (max-width: 768px) {
body {
font-size: 14px;
}
}
このようにメディアクエリを利用することで、異なるデバイスの画面サイズに応じたスタイルを適用し、ユーザーの可読性を向上させることが可能です。
また、レイアウトの変更にもメディアクエリは有効です。例えば、スマートフォンでは1カラム、PCでは2カラムのデザインに変更する場合、以下のように記述します。
.container {
display: flex;
flex-direction: column;
}
@media (min-width: 1025px) {
.container {
flex-direction: row;
}
}
このように、ブレイクポイントを適切に設定し、CSSにメディアクエリを記述することで、どのデバイスでもストレスなく閲覧できるサイトを実現できます。
6. 画像は高解像度ディスプレイに対応する
スマートフォンやタブレットの高解像度ディスプレイに適した画像を用意することが重要です。解像度の低い画像を使用すると、ぼやけたり粗く表示されることがあるため、最適な画像を準備する必要があります。
高解像度ディスプレイに対応するための方法として、まず通常の2倍サイズの画像を用意し、CSSで適切に縮小することで、画質を維持しながら適切なサイズで表示させることができます。また、アイコンやロゴなどの要素は、SVGを使用することで拡大しても劣化しないデザインを維持できます。
これにより、高解像度ディスプレイでも鮮明な表示が可能になり、ユーザーの視認性が向上します。
7. Google Chromeのディベロッパーツールで確認する
レスポンシブデザインが完成した後は、実際のスマートフォンやタブレットでどのように表示されるのかを確認することが重要です。しかし、すべてのデバイスで手動確認するのは現実的ではないため、Google Chromeのディベロッパーツールを活用すると効率的に検証が行えます。
ディベロッパーツールを使えば、画面サイズごとにどのように表示されるかをシミュレーションできるため、レイアウト崩れやボタンの押しにくさなどを事前に確認できます。

- Google Chromeを開く
- F12キーを押す
- Toggle Device Toolbarのアイコンをクリック
- Dimensions: Responsiveをクリック
- 各機種名を選択して、異なるデバイスの表示を確認
この機能を活用することで、実際のスマホ画面に近い状態でホームページのレイアウトをチェックできるため、レスポンシブデザイン対応が適切に行われているかを素早く検証できます。
レスポンシブデザイン設計の注意点
レスポンシブデザインを設計する際は、使いやすさと表示速度を意識することが重要です。ここでは、レスポンシブデザイン設計の注意点を紹介します。
スマートフォンを優先する
スマートフォンでの閲覧が主流となる中、スマホを基準にした設計が欠かせません。特に、Googleのモバイルファーストインデックスでは、モバイル版のサイトが検索順位の評価基準となるため、適切な対応が必要です。
スマートフォンを優先した設計を行うことで、ユーザーの利便性が向上し、SEOの評価にもつながります。
画像を軽くする
画像のデータサイズが大きいと、ページの読み込みが遅くなり、ユーザーの離脱やSEO評価の低下につながる可能性があります。
そのため、適切なサイズやフォーマット、圧縮を行い、表示速度を意識した最適化を行うことが重要です。無駄な読み込みを減らし、必要な画像だけを適切に表示できるよう調整しましょう。
フォントサイズとタップ範囲を最適化する
スマートフォンでは、画面が小さいため、文字の読みやすさとボタンの押しやすさを考慮することが重要です。フォントサイズは小さすぎると視認性が低下し、タップできる範囲が狭いと誤操作の原因になります。
適切なフォントサイズとタップ範囲を確保し、ストレスなく閲覧・操作できるデザインとしましょう。
横向きにした時のデザインも考慮する
スマートフォンやタブレットのユーザーは、縦向きだけでなく横向きでサイトを閲覧することもあるため、横向き表示のデザインも考慮する必要があります。特に、タブレットでは横向きの利用率が高い傾向があります。
そのため、横向きでもレイアウトが崩れず、コンテンツが適切に表示されるかを事前に検証することが大切です。ナビゲーションの配置や画像の表示サイズを調整し、横向き時にも視認性が損なわれないようにすることで、ユーザーの満足度を高めることができます。
ページの表示速度を意識する
ページの読み込み速度は、SEOにも直結する重要な要素です。特にモバイル環境では、回線速度が安定しないこともあるため、できるだけ軽量なページ設計を心がけることが求められます。
表示速度を向上させるためには、画像の圧縮・最適化、不要なJavaScriptやCSSの削減、キャッシュの活用、CDNの利用などが有効です。また、GoogleのPageSpeed Insightsを活用して、パフォーマンスを測定し、改善点をチェックするとよいでしょう。
レスポンシブデザインのテンプレート
レスポンシブデザインを一から制作するのは時間と手間がかかりますが、既存のテンプレートを活用することで、効率的にサイトを制作することが可能です。無料・有料を問わず、多くのテンプレートが提供されており、デザインや機能が豊富なものを選ぶことで、目的に合ったホームページ制作がスムーズに進みます。
例えば、Template PartyやCloud Templateでは、初心者でも扱いやすいレスポンシブ対応のテンプレートを多数提供しており、ダウンロードしてすぐに利用することができます。
デザインやレイアウトを自社のブランドに合わせて調整することで、オリジナリティのあるサイトに仕上げることができます。
レスポンシブデザインのまとめ
レスポンシブデザインは、異なるデバイスでも快適に閲覧できるホームページを作成するために欠かせない手法です。検索エンジンの評価向上や、ユーザーの利便性向上につながるため、ホームページ制作において重要な要素となります。
導入する際は、ターゲットの利用端末を考慮し、ブレイクポイントを適切に設定することが大切です。また、画像の軽量化やフォントサイズの調整、横向き表示の対応など、細かい設計にも注意を払うことで、より最適なデザインを実現できます。
レスポンシブデザインを適用することで、SEO対策にも効果的なホームページを制作でき、スマートフォン・PC問わず快適なユーザー体験を提供することが可能です。